江戸の今昔物語 ( 続き )
 火事で焼けたのは江戸市中の民家 ・ 武家屋敷だけではなく江戸城も火災の被害を受けましたが、城内からの出火だけではなく 時には江戸市中の火災による延焼もありました。
1607 年 12 月19 日には 田安口門 ( たやすぐちもん ) が延焼したのを皮切りに、前述した 1657 年の明暦 ( めいれき ) の大火では江戸城の 五層の天守閣も延焼により焼失しましたが 、以後明治維新まで再建されませんでした。
火事で焼けたのは江戸市中の民家 ・ 武家屋敷だけではなく江戸城も火災の被害を受けましたが、城内からの出火だけではなく 時には江戸市中の火災による延焼もありました。
1607 年 12 月19 日には 田安口門 ( たやすぐちもん ) が延焼したのを皮切りに、前述した 1657 年の明暦 ( めいれき ) の大火では江戸城の 五層の天守閣も延焼により焼失しましたが 、以後明治維新まで再建されませんでした。
 延享 4 年 ( 1747 年 ) に起きた江戸城 ・ 二の丸御殿炎上 ( 2 度目 ) の際には、それまで江戸城内に入ることを禁止されていた 「 町火消し 」 が入ることを許されて消火活動をおこないましたが、定火消し ・ 大名火消しよりも町火消しの消火能力が向上したからでした。さらに弘化元年 ( 1844 年 ) の江戸城の火災では、町火消しが総出動して城内の消火活動に従事しました。写真は皇居内にある、江戸城 天守閣の跡地です。
前述した 1607 年の延焼から、明治元年 ( 1868 年 ) 1 月 21 日の 二の丸御殿の火災 ( 4 度目 ) までの 261 年間に 36 件 の江戸城内の出火 ・ 延焼がありましたが、これは 7.25 年に 1 回 の割で江戸城が火災に遭ったことになります。
延享 4 年 ( 1747 年 ) に起きた江戸城 ・ 二の丸御殿炎上 ( 2 度目 ) の際には、それまで江戸城内に入ることを禁止されていた 「 町火消し 」 が入ることを許されて消火活動をおこないましたが、定火消し ・ 大名火消しよりも町火消しの消火能力が向上したからでした。さらに弘化元年 ( 1844 年 ) の江戸城の火災では、町火消しが総出動して城内の消火活動に従事しました。写真は皇居内にある、江戸城 天守閣の跡地です。
前述した 1607 年の延焼から、明治元年 ( 1868 年 ) 1 月 21 日の 二の丸御殿の火災 ( 4 度目 ) までの 261 年間に 36 件 の江戸城内の出火 ・ 延焼がありましたが、これは 7.25 年に 1 回 の割で江戸城が火災に遭ったことになります。
 そのため江戸城の大奥では、お目見え ( おめみえ、将軍に目通りが許される身分 ) 以下である 「 お火之番 」 ( おひのばん ) の女中達が、夜間だけでなく昼間も奥女中の部屋を、
そのため江戸城の大奥では、お目見え ( おめみえ、将軍に目通りが許される身分 ) 以下である 「 お火之番 」 ( おひのばん ) の女中達が、夜間だけでなく昼間も奥女中の部屋を、
火の用心、さっしゃりましょう ( なさりましょう )といいながら火災予防の見回りをしましたが、彼女たちは武芸にも長 ( た ) けていて 大奥を警備する役割も担っていました。 ( 6−2、江戸大火の原因とは )  大火の原因となったのは当時の家が燃え易い木と紙で出来たうえに 「 藁葺 ( わらぶき ) 屋根 」 ・ 「 茅葺 ( かやぶき ) 屋根 」 という庶民の家の造りで、出火の際には火の粉が近隣家屋の屋根に飛び火して、見る間に火災が拡大しました。記録に残る最初の江戸の大火は慶長 6 年 ( 1601 年 ) のことでしたが、大火後に幕府はそれらの燃え易い屋根を、少しは燃え難くなる 板葺 ( いたぶき ) 屋根にするように指導しました。
大火の原因となったのは当時の家が燃え易い木と紙で出来たうえに 「 藁葺 ( わらぶき ) 屋根 」 ・ 「 茅葺 ( かやぶき ) 屋根 」 という庶民の家の造りで、出火の際には火の粉が近隣家屋の屋根に飛び火して、見る間に火災が拡大しました。記録に残る最初の江戸の大火は慶長 6 年 ( 1601 年 ) のことでしたが、大火後に幕府はそれらの燃え易い屋根を、少しは燃え難くなる 板葺 ( いたぶき ) 屋根にするように指導しました。
 その後、豪華な大名屋敷が建築されるようになり、それに合わせて屋根には本瓦葺 ( ほんがわら ぶき、右の写真 ) が流行し、町家でも本瓦葺きにした建物が増加しました。しかし、1657 年に起きた明暦の大火後に幕府は突然方針を転換し、本瓦葺や瓦葺を 禁止することになりました 。
その後、豪華な大名屋敷が建築されるようになり、それに合わせて屋根には本瓦葺 ( ほんがわら ぶき、右の写真 ) が流行し、町家でも本瓦葺きにした建物が増加しました。しかし、1657 年に起きた明暦の大火後に幕府は突然方針を転換し、本瓦葺や瓦葺を 禁止することになりました 。 「 飛び火 」 に強いはずの瓦葺屋根が禁じられたのは、前述したように当時の消火方法であった風下の家々を予め破壊することにより火勢を弱め、延焼を防ぐことにより消火に導く 「 破壊消防 」 をしたところ、落下する屋根瓦で怪我をする火消し人足が多く出たためといわれています。左図は破壊消防のために、屋根瓦を落としているところ。
そのため次には町中の 「 わら葺 」 ・ 「 茅葺 」 屋根には土を塗らせ、 「 板葺 」 の屋根には土を塗り その上に蛎殻 ( かきがら ) か 芝を置くように命じました。
しかし 瓦葺き禁止令も 3 年後には解除 されたましたが、 東京市史稿 変災篇 第 4 「 候爵 浅野家回答 」 によれば、
「 飛び火 」 に強いはずの瓦葺屋根が禁じられたのは、前述したように当時の消火方法であった風下の家々を予め破壊することにより火勢を弱め、延焼を防ぐことにより消火に導く 「 破壊消防 」 をしたところ、落下する屋根瓦で怪我をする火消し人足が多く出たためといわれています。左図は破壊消防のために、屋根瓦を落としているところ。
そのため次には町中の 「 わら葺 」 ・ 「 茅葺 」 屋根には土を塗らせ、 「 板葺 」 の屋根には土を塗り その上に蛎殻 ( かきがら ) か 芝を置くように命じました。
しかし 瓦葺き禁止令も 3 年後には解除 されたましたが、 東京市史稿 変災篇 第 4 「 候爵 浅野家回答 」 によれば、
万治三年 ( 1660 年 ) 庚子 ( かのえ ね ) 二月六日、御大名様方 江戸御屋敷、此 ( これ ) 以後 瓦葺き苦しからざる旨 、公儀より仰せ出されるとあり 1660 年には、大名屋敷を中心に瓦葺き屋根にしてもよいとする御触れ書きを出して、武家屋敷 ・ 町家へも準用させましたが、前述した本瓦葺き ( ほんがわらぶき ) ではなく、それよりも軽い 桟瓦葺き ( さんがわらぶき、現代の瓦葺き ) になりました。 ( 6−3、火の用心 カチカチ )  江戸時代の出火の主な原因は炊事の火の不始末だけでなく、行灯 ( あんどん ) などの照明器具にも ロウソク や灯油の裸火 ( はだかび ) を使用したからでした。子供の頃 ( 1944 年まで ) に住んだ東京の豊島区 ・ 巣鴨では、毎年冬になると 「 夜回り番 」 を職業とする人がいて、夜遅く拍子木を カチ カチと叩きながら 「 火の用心 」 と声を出して町中を巡回していました。
江戸時代の出火の主な原因は炊事の火の不始末だけでなく、行灯 ( あんどん ) などの照明器具にも ロウソク や灯油の裸火 ( はだかび ) を使用したからでした。子供の頃 ( 1944 年まで ) に住んだ東京の豊島区 ・ 巣鴨では、毎年冬になると 「 夜回り番 」 を職業とする人がいて、夜遅く拍子木を カチ カチと叩きながら 「 火の用心 」 と声を出して町中を巡回していました。 これは敗戦直後 ( 1946 年 ) に住んだ埼玉県の秩父市にもありましたが、こちらは職業ではなく冬の間だけ町内の家から交代で当番に当たった人 2〜3 人が 「 火の番小屋 」 に泊まり込み、 2 時間おきに やはり拍子木を叩いて 「 火の用心 」 と言いながら町内を巡回し、火事に対する注意喚起と火事の発見の役目をしていましたが江戸時代の名残りでした。
これは敗戦直後 ( 1946 年 ) に住んだ埼玉県の秩父市にもありましたが、こちらは職業ではなく冬の間だけ町内の家から交代で当番に当たった人 2〜3 人が 「 火の番小屋 」 に泊まり込み、 2 時間おきに やはり拍子木を叩いて 「 火の用心 」 と言いながら町内を巡回し、火事に対する注意喚起と火事の発見の役目をしていましたが江戸時代の名残りでした。
 私も中学生の時に一度だけ土曜日の夜に 「 火の番小屋 」 に泊まり込み 「 火の用心 」 の巡回に加わりましたが、付属する火の見櫓 ( ひのみやぐら ) には火事を知らせる半鐘 ( はんしょう ) がありました。
私も中学生の時に一度だけ土曜日の夜に 「 火の番小屋 」 に泊まり込み 「 火の用心 」 の巡回に加わりましたが、付属する火の見櫓 ( ひのみやぐら ) には火事を知らせる半鐘 ( はんしょう ) がありました。ちなみに半鐘とは江戸時代に寺院の梵鐘 ( ぼんしょう、通常 口径が 1 尺 8 寸 = 約 54.5 センチ 以上 ) に比べて小さい釣り鐘を半鐘と呼び、高い音を出し仏事以外に主に火事などの警報目的で使われました。 ( 6−4、消防署の望楼、火の見櫓 )  私が子供の頃は消防署の建物といえば望楼 ( ぼうろう、火の見櫓 ) が付きものでしたが、そこでは昼夜を問わず消防署員が望楼の上を巡回して火災の発見に務めているのが見えました。ほとんどが屋根だけある吹きさらしの構造でしたが、敗戦 ( 1945 年 ) 後にできた新しい消防署の望楼は窓 ガラスで覆われました。
前述のように火の見櫓は江戸初期の定火消 ( じょうびけし ) の頃からありましたが、明治維新になると新政府は国の近代化を進めるために、欧米諸国からいわゆる 「 お雇い外国人 」 と称する学者や技術者たちを日本に呼び寄せ近代的技術 ・ 制度 ・ 知識の習得を図りました。
そのうちの一人で イギリス人の J ・ M ・ ジェームス ( James ) が、「 各区ゴトニ望火楼ヲ設ケ・・・云々 」 という 望火楼( ぼうか ろう ) の設置に関する建白書 を東京府知事に提出し、その設置を促しました。これを契機に警視庁消防署 ( 現 ・ 東京消防庁 ) や、消防分署 ( 現 ・ 消防署 ) などに望楼が建てられ、東京市内では火の見櫓がかなり増設されました。
私が子供の頃は消防署の建物といえば望楼 ( ぼうろう、火の見櫓 ) が付きものでしたが、そこでは昼夜を問わず消防署員が望楼の上を巡回して火災の発見に務めているのが見えました。ほとんどが屋根だけある吹きさらしの構造でしたが、敗戦 ( 1945 年 ) 後にできた新しい消防署の望楼は窓 ガラスで覆われました。
前述のように火の見櫓は江戸初期の定火消 ( じょうびけし ) の頃からありましたが、明治維新になると新政府は国の近代化を進めるために、欧米諸国からいわゆる 「 お雇い外国人 」 と称する学者や技術者たちを日本に呼び寄せ近代的技術 ・ 制度 ・ 知識の習得を図りました。
そのうちの一人で イギリス人の J ・ M ・ ジェームス ( James ) が、「 各区ゴトニ望火楼ヲ設ケ・・・云々 」 という 望火楼( ぼうか ろう ) の設置に関する建白書 を東京府知事に提出し、その設置を促しました。これを契機に警視庁消防署 ( 現 ・ 東京消防庁 ) や、消防分署 ( 現 ・ 消防署 ) などに望楼が建てられ、東京市内では火の見櫓がかなり増設されました。
 出火の際の半鐘の打ち方について警視消防本署 ( 現 ・ 消防庁 ) の規定によれば、
出火の際の半鐘の打ち方について警視消防本署 ( 現 ・ 消防庁 ) の規定によれば、
 東京消防庁の統計によれば、望楼による火災の発見率は昭和 28 年 ( 1953 年 ) には 11.8 パーセント あったものが、昭和 38 年 ( 1963 年 ) には 3.3 パーセント、昭和 44 年 ( 1969 年 ) には 2 パーセントとなりました。
東京消防庁の統計によれば、望楼による火災の発見率は昭和 28 年 ( 1953 年 ) には 11.8 パーセント あったものが、昭和 38 年 ( 1963 年 ) には 3.3 パーセント、昭和 44 年 ( 1969 年 ) には 2 パーセントとなりました。高度経済成長により 各戸に電話が普及し 建物の高層化が進んだ昭和 47 年 ( 1972 年 ) には、わずか 0.26 パーセント と落ち込んだために、翌昭和 48 年 ( 1973 年 ) 6 月 1 日から、都内ではすべての望楼の運用を停止し火災発見の役目を終えました。 参考までに昭和 43 年 ( 1968 年 ) 当時の電話事情については、我が家に電話 ( 固定電話 ) が架設されたのは、電電公社 ( 日本電信電話公社、民営化され現 ・ NTT ) への 申し込みから 1 年半後 のことであり、しかも何万円かの電話債券 ( 加入権 ) を購入する必要がありました。書類さえ整えば数日以内に、携帯電話や スマホ を入手できる現代とは大違いでした。 ( 6−5、火の用心の語源 )  1957 年に開設された南極の昭和基地とは、現在では インテルサット ( INTELSAT、International Telecommunication Satellite Organization、国際電気通信衛星機構 ) の衛星を利用した通信が 2004 年から可能となっていて、電話、FAX、メールも利用できますが、昔は国際電電 ( 国際電信 電話株式会社、KDDI ) の 電信 ( トン ・ ツー ) による電報だけが頼りでした。
昭和基地で越冬する隊員宛てに夫人から届いた簡単明瞭で日本一短い電報がありますが、それは僅か三文字の 「 アナタ 」 でした。ところで日本一短い手紙として広く知られているものに、下記の手紙文があります。
1957 年に開設された南極の昭和基地とは、現在では インテルサット ( INTELSAT、International Telecommunication Satellite Organization、国際電気通信衛星機構 ) の衛星を利用した通信が 2004 年から可能となっていて、電話、FAX、メールも利用できますが、昔は国際電電 ( 国際電信 電話株式会社、KDDI ) の 電信 ( トン ・ ツー ) による電報だけが頼りでした。
昭和基地で越冬する隊員宛てに夫人から届いた簡単明瞭で日本一短い電報がありますが、それは僅か三文字の 「 アナタ 」 でした。ところで日本一短い手紙として広く知られているものに、下記の手紙文があります。
一筆啓上 ( いっぴつ けいじょう ) 火の用心 お仙泣かすな 馬肥やせこれは徳川家康配下の武将であった 「 本多作左衛門重次 」 が、天正 3 年 ( 1575 年 ) の織田信長と徳川家康の連合軍対 武田勝頼との戦闘である 「 長篠の戦い 」 の陣中から、妻に宛てて書いた手紙でした。  この手紙に出てくる 「 火の用心 」 こそが日本で最初に使われたという説が有力となっていて、本多作左衛門重次が 火の用心 の言葉の生みの親 と言われています。
なお文中の 「 お仙 」 とは彼の跡取り息子である 仙千代のことで、後に越前国 ( 福井県 ) 丸岡藩主になった本多成重のことでした。茨城県 ・ 取手市にある本願寺は本多重次の菩提寺で、そこには 一筆啓上の碑があります。
この手紙に出てくる 「 火の用心 」 こそが日本で最初に使われたという説が有力となっていて、本多作左衛門重次が 火の用心 の言葉の生みの親 と言われています。
なお文中の 「 お仙 」 とは彼の跡取り息子である 仙千代のことで、後に越前国 ( 福井県 ) 丸岡藩主になった本多成重のことでした。茨城県 ・ 取手市にある本願寺は本多重次の菩提寺で、そこには 一筆啓上の碑があります。
[ 7 : 暦と季節 ]日本の暦は平安時代に中国からもたらされた 太陰暦 ( たいいんれき ) を使用し 、後にはより正確な太陰太陽暦 ( たいいん たいようれき ) を使用していましたが、これは太陰 ( 月 ) の運行 ( 満ち欠け ) を基本とする 「 太陰暦 」 と、太陽の運行を基本とする 「 太陽暦 」 の周期を組み合わせて暦が季節と 大きく ズレない ように ( 注 参照 ) 工夫されたものでした。注 : イスラム暦太陰暦では満月 ( または新月 ) から次の満月 ( 新月 ) までを 1 ヶ月 ( 朔望月、 さくぼうげつ ) としますが、それは太陽暦にすれば 29.530日 に相当します。12 ヶ月では 354.36日 となり、太陽暦の 365 日に比べて 約 11 日 短くなります 。これに対する修正をどのようにするかが ポイントです 。 朔望月 ( 月の満ち欠けの周期 ) を 1 ヶ月とする太陰太陽暦では 1 ヶ月は 29 日か 30 日ですが、 「 30 日 」 の 大 の月と 「 29 日 」 の 小 の月を設けて調整する必要がありました。しかし現在のように、 西向く士 ( にしむく さむらい、2・4・6・9・十一 ) 小の月 のように、どの月が 「 小の月 」 でどの月が 「 大の月 」 かは一定ではなく、暦を見なければ誰にも分かりませんでした。 さらに太陰暦の 1 年は 12 ヶ月とは限らず、前述したように 1 年の日数が太陽暦に比べて年間で 11 日も足りないために 3 年に一度は 閏年 ( うるうどし ) を設け、その年には 閏月 ( うるう づき ) を加えて 1 年を 13 ヶ月 にしました。 太陰太陽暦では 毎月 15 日が必ず満月 ( 望、ぼう ) になり、月初めの 1 日 ( ついたち ) には月が地球の影に隠れて見えない 朔 ( さく、新月 ) になりました。 ちなみに月の第一日のことを 「 ついたち 」 とするのは、月が始まる 「 月立ち 」 が転じたものとも言われています。 陰暦 8 月 を中秋 ( ちゅうしゅう ) ともいいますが、空気が澄んで月が美しく見える 8 月 15 日の 満月 ( 十五夜 ) を観賞する習慣は平安時代の延喜 9 年 ( 909 年 ) に、宮中で行われた 「 仲秋節 」 が始まりで、当時は詩歌管絃 ( しいか かんげん、漢詩や和歌を吟じ、楽器を奏でること ) の催しのみで、月に供え物をする習慣はなかったとされます。  また池に龍頭船 ( りょうとうせん ) や 鷁首船 ( げきすせん ) を浮かべて、水面 ( みなも ) に映る月を愛 ( め ) でたりしました。
その後、日本に古くからあった秋の豊作を祈願する初穂祭りと結びつき、江戸時代には庶民の間で月見が盛んになり、里芋や団子を供え、すすきや秋草を飾り 農民が収穫を感謝し、 秋の豊作を祈りました。ちなみに陰暦 9 月の異名である長月 ( ながつき ) とは、秋も深まり次第に夜が長くなっていく 「 夜長月 」 に由来するといわれています。
また池に龍頭船 ( りょうとうせん ) や 鷁首船 ( げきすせん ) を浮かべて、水面 ( みなも ) に映る月を愛 ( め ) でたりしました。
その後、日本に古くからあった秋の豊作を祈願する初穂祭りと結びつき、江戸時代には庶民の間で月見が盛んになり、里芋や団子を供え、すすきや秋草を飾り 農民が収穫を感謝し、 秋の豊作を祈りました。ちなみに陰暦 9 月の異名である長月 ( ながつき ) とは、秋も深まり次第に夜が長くなっていく 「 夜長月 」 に由来するといわれています。
[ 8 : 時刻の決め方と、知らせる方法 ]多くの文化を大陸から輸入した日本では、古代から時刻の観念があったとされますが、それらの詳細を知る資料 ( たとえば日時計の資料など ) は全くありません。 5 世紀になると大和朝廷により日本統一がほぼ完成し 中央集権政治が確立すると、朝廷の行事を規定したり法令を実施するに当たって、次第に時刻を明示することが必要になりました。 日本書紀によれば第 34 代、舒明 ( じょめい ) 天皇の 8 年 ( 636 年 ) に、朝臣 ( あそん、朝廷に仕える臣 ) の参内時刻を規定した詔勅が記されていますが、これが公式に時刻を示した最初の文書とする説があります。 その 時刻は 十二支 による辰刻 ( たつのこく ) で示されていましたが、江戸時代と同じ時刻制であると 仮定すれば 、午前 8 時頃になります。 日本書紀によれば第 37 代、斉明( さいめい ) 天皇 在位 655〜661 年 ) の 6 年 ( 660 年 ) 5 月に、中大兄皇子 ( なかのおおえのみこ、後の第 38 代、天智天皇 ) が初めて 漏刻 ( ろうこく、水時計 ) を作り民に時を知らせたとありますが、これが日本で歴史上最初の時計であり、報時 ( ほうじ ) の始まりでした。 奈良時代の 718 年には時刻を保持するために朝廷の陰陽寮 ( おんみょうりょう ) に 2 人の漏刻博士という官吏が 置かれ、この下に 20 人の守辰丁 ( しゅ しんちょう ) / 別名を時守 ( ときもり ) が置かれ、時刻を監視し鐘鼓 ( しようこ ) を打って時を知らせました。しかし正確な漏刻 ( 水時計 ) の作成は極めて困難であり、その数も極めて少なく宮中以外には重要な役所に僅かに置かれていました。( 8−1、定時法 ) 時刻の決め方には 定時法と 不定時法 がありますが、まずは簡単な定時法から説明します。 定時法 とは現在行われている時間の決め方で 昼夜 ・ 季節に関係なく 、1 日の長さを等分して時刻を決める時刻法のことです。 日本で 「 定時法 」 を用いるようになったのは、太陰暦の明治 5 年 ( 1872 年 ) 11 月 9 日付 ( 太陽暦では 12 月 9 日 ) の太政官布告第 337 号の、 太陰暦ヲ廃シ太陽暦ヲ頒行 ( はんこう、広く一般に配布すること ) ス。來 ( きた ) ル 十二月三日ヲ以テ、明治六年一月一日ト被定候事 ( さだめられ そうろうこと )に基づき太陰暦の明治 5 年 12 月 3 日を、 太陽暦 ( グレゴリオ暦 ) の ( 1873 年) 明治 6 年 1 月 1 日とすることにしました。 この太陽の動きに合わせた 「 太陽暦 」 は、1582 年に 第 226 代 ローマ教皇 ( 在位 : 1572 年〜1585 年 ) の グレゴリウス ( Gregorius ) 13 世が、それまでの ユリウス ・ カエサル ( Julius Caesar、ジュリアス シーザー ) 暦を改正して制定した暦法ですが、明治新政府が 太陽暦 ( グレゴリオ、Gregorio 暦 ) を採用したことにより、それまでの旧暦 ( 太陰太陽暦 ) や不定時法による時刻表示を廃止して、1 年は 365 日、1 日は 24 時間とし、時刻表示も 何時何分という風に改められました。 [ 8−2、不定時法と、刻 ( とき ) の表示 ]  私の趣味の 一つは 藤沢周平の時代小説や 長谷川 伸 ( しん ) の股旅物、彼の弟子で時代小説家の池波正太郎の作品や、岡本綺堂 ( きどう ) の 「 半七捕り物帳 」 などを読むことですが、 「 草木も眠る丑 三つ ( うしみつ ) どき などと記した文章を読むと、はて何時のことかと最初は分かりませんでした。
江戸時代では時間をおおらかに捉え、時刻の決め方には 不定時法 ( ふていじほう ) を採用していました。これは 日の出前の黎明 ( れいめい、夜明けの薄明かり ) から 日没後の薄暮 ( はくぼ、夕暮れの薄明かり ) までを 昼間 として、それ以後から日の出前の黎明 ( れいめい ) までを 夜間 として、それぞれを 6 等分し、これを 一刻 ( いっとき ) として時間を計る方法で、 1 日は 12 刻 ( とき ) でした。
刻 ( とき ) 以下の時刻の表し方としては時代により異なりますが、1 刻 ( とき ) をさらに 4 等分して、それぞれ 「 一つ 」 ・ 「 二つ 」 ・ 「 三つ 」 と呼びましたが、左上図の 丑 ( うし ) 三つ を参考にして下さい。
私の趣味の 一つは 藤沢周平の時代小説や 長谷川 伸 ( しん ) の股旅物、彼の弟子で時代小説家の池波正太郎の作品や、岡本綺堂 ( きどう ) の 「 半七捕り物帳 」 などを読むことですが、 「 草木も眠る丑 三つ ( うしみつ ) どき などと記した文章を読むと、はて何時のことかと最初は分かりませんでした。
江戸時代では時間をおおらかに捉え、時刻の決め方には 不定時法 ( ふていじほう ) を採用していました。これは 日の出前の黎明 ( れいめい、夜明けの薄明かり ) から 日没後の薄暮 ( はくぼ、夕暮れの薄明かり ) までを 昼間 として、それ以後から日の出前の黎明 ( れいめい ) までを 夜間 として、それぞれを 6 等分し、これを 一刻 ( いっとき ) として時間を計る方法で、 1 日は 12 刻 ( とき ) でした。
刻 ( とき ) 以下の時刻の表し方としては時代により異なりますが、1 刻 ( とき ) をさらに 4 等分して、それぞれ 「 一つ 」 ・ 「 二つ 」 ・ 「 三つ 」 と呼びましたが、左上図の 丑 ( うし ) 三つ を参考にして下さい。
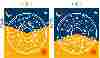 しかし不定時法では昼と夜の長さが等しいのは春分と秋分の時期だけであり、夏は夏至 ( げし ) の頃を頂点として昼の間が最も長く、冬には冬至 ( とうじ ) の頃に昼の時間が最も短くなるのは当然でした。
夏至の頃における昼間の 1 刻 ( とき ) は 約 2 時間 40 分 であるのに対して、冬至における昼間の 1 刻 ( とき ) の長さは 約 1 時間 50 分程度 となり、その差は約 50 分もありました。
しかし不定時法では昼と夜の長さが等しいのは春分と秋分の時期だけであり、夏は夏至 ( げし ) の頃を頂点として昼の間が最も長く、冬には冬至 ( とうじ ) の頃に昼の時間が最も短くなるのは当然でした。
夏至の頃における昼間の 1 刻 ( とき ) は 約 2 時間 40 分 であるのに対して、冬至における昼間の 1 刻 ( とき ) の長さは 約 1 時間 50 分程度 となり、その差は約 50 分もありました。
( 8−3、時の鐘 ) 江戸時代の生活において時計とは無縁の町人や下級武士にとっては、不定時法の刻 ( とき ) を知る方法がなく不便でした。そこで幕府は江戸城内で 「 太鼓 」 を叩いて刻 ( とき ) を知らせることにしましたが、聞こえる範囲が狭いので寛永 3 年 ( 1626 年 ) に、日本橋 本石町 ( ほんこくちょう、現 ・ 日本橋 本町 4 丁目 ) に 200 坪の土地を与えて、鐘楼を作らせたのが 「 時の鐘 」 のはじまりでした。  なおこの鐘の聞こえる範囲を 48 ヶ町として、一軒の家から鐘撞料 ( かねつきりょう ) を 4 文くらいずつ徴収していましたが、岡本綺堂 ( きどう ) の 「 風俗 江戸物語 」 によれば、江戸市中には 後述する寺の他に目黒 ・ 本所 ・ 四谷 ・ 市ヶ谷 ・ 赤坂など 9 箇所の寺 などに時の鐘がありました。
なおこの鐘の聞こえる範囲を 48 ヶ町として、一軒の家から鐘撞料 ( かねつきりょう ) を 4 文くらいずつ徴収していましたが、岡本綺堂 ( きどう ) の 「 風俗 江戸物語 」 によれば、江戸市中には 後述する寺の他に目黒 ・ 本所 ・ 四谷 ・ 市ヶ谷 ・ 赤坂など 9 箇所の寺 などに時の鐘がありました。松尾芭蕉 ( ばしょう、1644〜1694 年 ) の俳句に 花の雲 鐘は上野か浅草かがありますが、当時隅田川に近い深川の芭蕉庵に住んでいた彼が時を知らせる鐘を聞き、上野東叡山 ( とうえいざん ) 寛永寺の鐘か、浅草金龍山 ( きんりゅうざん ) 浅草寺の鐘か と句に詠んだもので、時の鐘は上野の寛永寺と浅草の浅草寺にもありました。 鐘のつき方は、夜の 12 時つまり 「 夜 九つ 」 から始め、最初必ず 「 捨て鐘 」 と称する カウント されない鐘を 三回つきました。したがって 12 回鐘をつくと、夜 九つということになります。それから 2 時間ごとの間隔で 「 夜 八つ、午前 2 時 」・ 「 夜 七つ、午前 4 時 」・ 日の出前の 「 明け六つ、午前 6 時 」・ 「 朝 五つ、午前 8 時 」・ 「 昼 四つ、昼 10 時 」 ・ 「 昼 九つ、昼 12 時 」 以下省略の鐘をつき時を知らせました。 幕末の天保年間に作られた 「 こちゃえ節 」 を基に 道中唄 ( うた ) を民謡にした 「 お江戸 日本橋 」 がありますが、その歌詞に とあります。2 番の歌詞は 「 六郷 渡れば川崎の 万年屋 鶴と亀との よね ( 米 ) 饅頭 コチャ 神奈川 急いで 程ヶ谷へ こちゃえこちゃえ 」 です。 昔の旅は早立ち早着きが原則でしたので、七つ ( 午前 4 時頃 ) に出発の際には照明用の提灯が必要でしたが、日本橋から 6 キロ離れた高輪の大木戸 ( おおきど ) を通過する頃には夜が明けて来たので、提灯の火を消すという意味でした。 「 行列揃えて 」 とありますが、この行列とは 「 大名行列 」 のことだと 誤解する人が多い のですが、そうではなく 後の ( 9−3 ) の項で説明します。また歌詞の 2 番に 「 神奈川 急いで 」 とありますが、前述のように天保年間 ( 1830〜1843 年 ) に作られた唄であり、当時の神奈川 ( 横浜 ) は ペリーの来航 ( 嘉永 6 年、1853 年 ) 以前は 「 さびれた漁村 」 のため、見るべき名所、賞味すべき名物が何も無いので急いで通過する意味でした。なお右上の絵は雪景色の日本橋です。  1603 年 ( 慶長 8 年 ) に徳川家康によって初めて架橋された日本橋は、五街道 ( 東海道 ・ 中山道 ・ 日光街道 ・ 甲州街道 ・ 奥州街道 ) の起点となり、その界隈 ( かいわい ) は人々の往来で賑わいました。写真は明治初期の日本橋ですが、橋のたもとには船着き場がありました。
1603 年 ( 慶長 8 年 ) に徳川家康によって初めて架橋された日本橋は、五街道 ( 東海道 ・ 中山道 ・ 日光街道 ・ 甲州街道 ・ 奥州街道 ) の起点となり、その界隈 ( かいわい ) は人々の往来で賑わいました。写真は明治初期の日本橋ですが、橋のたもとには船着き場がありました。
[ 8−4、干支 ( えと ) による刻 ( とき/こく ) の呼び名 ] 時刻の別の呼び名には 干支 ( えと ) による方法もありましたが、日付が変わる真夜中を子 ( ね ) の刻 ( とき/こく ) として 12 等分した時刻に干支の 十二支を割り当て、それぞれ子の刻 ( ねのとき/こく ) ・ 丑の刻 ( うしのとき/こく ) −−−としました。一刻 ( とき/こく ) は約 2 時間になりますが、詳しくは下表を参照してください。
現在の我々にとっては不便な不定時法による刻 ( とき ) も、照明環境の未発達な江戸時代には夜が明けると起きて働き、日が暮れると寝る生活 パターンの多かった町人 ・ 農民にとっては、目に見える明るさ、つまり日の出と日の入りを基準とした“不定時法”の方が分かり易く合理的だったのかもしれません。 [ 9 : 江戸時代の雇用制度と、会計年度との関係 ]日本における会計年度は政府 ・ 地方自治体などの公共機関から大小の株式会社まで現在は、毎年 4 月 1 日から始まり翌年の 3 月 31 日までの期間と定められていますが、江戸時代はどのようになっていたのでしょうか。 都市住民である町人や武家が人を雇用する場合について述べますと、地方からの出稼ぎ労働者 ( 下男 ・ 下女 ) については、 1 年を契約期間 と定め、それ以上の雇用契約の更新をしない いわゆる 「 出代わり 」 ( でがわり ) という制度がありました。 その理由は同じ奉公人を何年も続けて雇うことにより主人と奉公人との間で 密接な 「 主従関係 」 が生じることを幕府が嫌い、雇用者である主人に対して 奉公人の長期雇用を法令により禁止したのでした。現代風にいえば、 単純労働者の長期雇用の禁止 でした。 江戸時代初期には経済の先進地帯であった京都の雇用事情を見ると、慶長 15 年 ( 1610 年 ) 2 月に京都所司代 ( しょしだい、京都に駐在する江戸幕府の職名 ) が奉公人の出代 ( でが ) わり日を、毎年 2 月 2 日 に定める旨の布告を出していますが、江戸の場合も元和元年 ( 1615 年 ) 頃までは 毎年 2 月に 「 出代 ( でが ) わり 」 つまり奉公人の総入れ替えがおこなわれていました。 ところが、江戸幕府の公式記録である徳川実記の中にある 「 厳有院殿 ( 4 代将軍 徳川家綱の戒名 ) 御実記 巻 3 」 の承応元年 ( 1652 年 ) 正月 4 日付、「 代官宛 堤防、城米及び所務心得 」 布告の要点によれば、( 前略 ) 毎年 3 月 5 日より 会計をはじめ 、前年の分中勘定をなし、その余 ( よ、あまり ) は皆済 ( かいさい、完済の意味 ) すべし。 ( 中略 ) 徭夫 ( ようふ、日雇い ) の俸 ( ほう、賃金 ) はその日限りに与うべし。とあり、会計年度をそれまでの 2 月 2 日から以後 3 月 5 日に変更し 、それまでの奉公人にはその日を限りに賃金を払い、 新しい奉公人と入れ替わりました。 この会計年度は幕末まで続きました。 この布告の 太陰太陽暦の 3 月 5 日 が明治新政府による 太陽暦採用 の際に、他のもろもろの事柄と共に 約 1 ヶ月ずれた 4 月 1 日 に読み替えられた のだそうです 。その後も会計年度がいろいろ変更されましたが、最終的には明治 17 年 ( 1884 年 ) 10 月の太政官達 89 号により現在と同じ 4 月〜 3 月制となりました。その理由は当時の主要税目だった地租徴収に最も好都合であったからとされています。 ( 9−1、各国の会計年度 ) 参考までに会計年度は、各国により異なります。
イギリス ・ インド ・ パキスタン ・ デンマーク ・ カナダなど 韓国 ・ フランス ・ ドイツ ・ オランダ ・ ベルギー ・ スイス ・ ロシア ・ 中国 ・ 南米諸国など ノルウェー ・ スウェーデン ・ ギリシア ・ フィリピン ・ オーストラリアなど アメリカ ・ タイ ・ ミャンマー ・ ハイチなど ( 9−2、その他の雇用形態 ) 江戸に常住しない単純労働の出代 ( でが ) わりは前述のように 1 年の雇用契約でしたが、それ以外の雇用契約もありました。
 「 年季者 」 は親方や主人と同じ人別 ( にんべつ、戸籍に相当 ) に入れられ衣食住を与えられながら職業教育を受けました。商家の場合は丁稚 ( でっち ) になると雑用の間にまず 「 読み ・ 書き ・ そろばん 」 を習い 、手代 ( てだい ) ・ 番頭へと経験年数と本人の能力によって昇格し、呼び方も店での待遇も違ってきました。
「 年季者 」 は親方や主人と同じ人別 ( にんべつ、戸籍に相当 ) に入れられ衣食住を与えられながら職業教育を受けました。商家の場合は丁稚 ( でっち ) になると雑用の間にまず 「 読み ・ 書き ・ そろばん 」 を習い 、手代 ( てだい ) ・ 番頭へと経験年数と本人の能力によって昇格し、呼び方も店での待遇も違ってきました。( 9−3、初のぼり と 行列揃えて ) ここで ( 8−3 ) で述べた道中唄の 「 お江戸日本橋 」 を再掲します。 お江戸 日本橋、七つ立ち / 初のぼり 行列揃えて あれわいさのさ / こちゃ高輪 夜明けで提灯消す / こちゃえこちゃえここでいう 「 初のぼり 」 とは、文字通りに解釈すると初めて上方に 「 上る 」 ことですが、後述する江戸日本橋に支店を持つ商店の本店は 当時伊勢 ・ 近江 ・ 京都など関西にあり、従業員は犯罪防止の観点から身元が知れた同じ村などの縁故者を採用して江戸に派遣し、江戸での従業員採用を決してしませんでした。 丁稚小僧 ( でっち こぞう ) から勤め出し 9 〜 10 年経つと 初めて 50 〜 60 日程度の長期休暇 が与えられ、出身地である関西の故郷に帰省することが許されましたが、これをその当時 「 初のぼり 」 と呼びました。 後述する日本橋の呉服商 越後屋 ( 三越 デパートの前身 ) には当時数百人の従業員がいましたから、 「 初のぼり 」 の者も数人ではなかったはずで、さらに同業者の 「 初のぼり 」 の連中も一緒になり、これも道中における防犯の目的からなるべく集団で旅をさせましました。それらを店の番頭が、東海道経由で江戸を出入りする際の関門である 「 高輪の大木戸 」 ( おおきど ) まで修学旅行生のように引率して行き、江戸から無事に送り出しましたが、前述の歌詞はこの意味だとする説があります。 なお結婚については番頭になると初めて妻帯が許されましたが、 相手は郷里の女性に限られ しかも妻を江戸に連れてくることは許されず、年に一度の長期休暇をもらい故郷に帰る単身赴任でした。30 代後半 〜 40 代前半まで無事に勤めれば 「 のれん分け 」 として多額の退職金をもらい、多くは故郷に帰り商売を始めました。 職人の場合 年季が明けると同業 ・ 同職の間の認知を受ける 「 ひろめ 」 が行われて、一人前の職業人となり、主家からの独立が許されました。ただし職人の場合は本人の適性の関係もあって、一人前の職人としての技量を習得できない 「 年季崩れ 」 ( ねんきくずれ、職人不適格者 ) も多く、その場合はそれまでの食い扶持 ・ 仕着せ ( 衣料 ) ・ その他の経費を親方に弁償することが定められていました。商家の 「 年季者 」 も同様でした。 ( 9−4、下り物と、下らない物 ) 江戸の町は 京 ・ 大坂 ( 大阪 ) より遙かに遅れて誕生したために、江戸時代の中頃までは文化 ・ 産業面で上方 ( かみがた ) より遅れていました。身の回りの品々から酒や菓子に至るまで、京 ・ 大坂から船で輸送されてきた品物、つまり 「 下り物 」 ( くだりもの ) の方が、それ以外の関東周辺で作られた商品 ( つまり下らない品物 ) よりもはるかに上質でした。 そこで下り物と 、 く だらない物 ( 品質が粗悪で価値が低い物 ) という言葉が生まれましたが、利益に敏感な上方商人がこれに目を付け競って江戸に支店を設けました。なお 「 下り物 」 の消費は江戸市中だけに限られ、江戸から地方に転売することは禁じられていて、御三家の 一つである水戸家の要望でも 「 下り物の清酒 」 を水戸に送り出すことはできませんでした。  伊勢の越後屋 ( 後の 三越 デパート ) ・ 近江商人の大村彦太郎が開いた後の 白木屋 デパート ・ 京都の呉服屋、 大文字屋 などが江戸に支店を設けました。写真は江戸日本橋 大伝馬町に店を構えた 丸に大の文字を描いた 「 のれん 」 の大文字屋 ( 1903 年頃 ) で、後に大丸 デパートになりました。
下り物の中でも最も利益が大きい商品は衣料品でしたので、江戸日本橋には大きな呉服屋が多く店を出しました。その中で代表的なのが伊勢松坂の商人 ・ 三井高利が開いた越後屋であり、 「 現金、掛け値なし 」 の商法で大当たりしました。
伊勢の越後屋 ( 後の 三越 デパート ) ・ 近江商人の大村彦太郎が開いた後の 白木屋 デパート ・ 京都の呉服屋、 大文字屋 などが江戸に支店を設けました。写真は江戸日本橋 大伝馬町に店を構えた 丸に大の文字を描いた 「 のれん 」 の大文字屋 ( 1903 年頃 ) で、後に大丸 デパートになりました。
下り物の中でも最も利益が大きい商品は衣料品でしたので、江戸日本橋には大きな呉服屋が多く店を出しました。その中で代表的なのが伊勢松坂の商人 ・ 三井高利が開いた越後屋であり、 「 現金、掛け値なし 」 の商法で大当たりしました。
 幕末期に 一時衰退しましたが明治 37 年 ( 1904 年 ) に三井の 「 三 」 と越後屋の 「 越 」 の字から 「 三越呉服店 」 と名前を変えて、日本における百貨店 ( デパート ) の先駆 ( さきがけ ) である 三越 デパートとなりました。右の写真は東京 日本橋にある、 三越 デパート本店です。
幕末期に 一時衰退しましたが明治 37 年 ( 1904 年 ) に三井の 「 三 」 と越後屋の 「 越 」 の字から 「 三越呉服店 」 と名前を変えて、日本における百貨店 ( デパート ) の先駆 ( さきがけ ) である 三越 デパートとなりました。右の写真は東京 日本橋にある、 三越 デパート本店です。 ちなみに江戸時代の越後屋には使用人が 数百人もいて、40 人の手代が客の応対に当たり、数十人の仕立て職人を抱え 、依頼があれば 一晩で着物を縫い上げて客の求めに応じるのが自慢でした。左図は越後屋の店先で、左側に 「 えちご 」 の文字が右側に 三井の家紋が見えます。
ちなみに江戸時代の越後屋には使用人が 数百人もいて、40 人の手代が客の応対に当たり、数十人の仕立て職人を抱え 、依頼があれば 一晩で着物を縫い上げて客の求めに応じるのが自慢でした。左図は越後屋の店先で、左側に 「 えちご 」 の文字が右側に 三井の家紋が見えます。
[ 10 : 跡取り息子と娘婿 ( むすめ むこ ) ]日本では 「 古事記 」 ・ 「 日本書紀 」 に記された神代の昔から 高貴なお方は 一夫多妻でしたが、平安時代でも事情は変わらず紫式部が記した源氏物語 ( 1001 〜 1005 年の間に書き始め ) の冒頭の文章にも、いづれのおん時にか 女御 更衣 あまた侍ひ 給ひけるなかに [ その意味 ]とあります。女御 とは中宮より位が下で天皇の寝所に侍した女性のことであり、 更衣とは同じく女御より格下の女性で大納言以下の貴族の娘です。養老 2 年 ( 718 年 ) に公布された養老律令 ( ようろう りつりょう ) の 後宮職員令 ( ごくう しきいん りょう ) によれば、朝廷の後宮に仕える女官の階位 ・ 定数 ・ 出身の家柄などについて定められていて、皇后を含めて 合計 10 人までの女性 を天皇の傍に侍らせることができると規定していました。 戦国時代になるとその傾向はさらに強まり、徳川時代になると第 11 代将軍、徳川家斉 ( いえなり ) のように、正妻の他に何十人もの妾を持ち、50 人以上の子を産ませた例もありました。これは平安時代以後に武士に与えられた 知行 ( ちぎょう、土地の支配権 ) を時には武力で守る必要があり、世襲により既得権を維持するためには男子が必要でした。 男子の誕生まで 妾を何人持とうが制度上の制約はありませんでした。 ( 10−1、商家の後継ぎは娘むこ ) 武家の世継ぎには男子の誕生が必須でしたが、家業や職業によっては 女子の誕生 が尊重される場合もありました。一例を挙げると相撲の親方にとっては、男児よりも女児の出生が絶対に好まれました。なぜなら親方の息子が将来横綱や幕内力士になれる確率は極めて少ない ( 昔は横綱になれたのは新弟子 千人に 1 人の割合とされた ) のですが、娘であれば将来有望な力士を選び結婚させることができ、部屋の後継者を確保できるからでした。 卑近な例を挙げると横綱大鵬の 三女と結婚した元関脇 貴闘力が大鵬部屋の部屋付き親方 ( 大嶽、おおたけ ) となり、その後大鵬部屋を継承しましたが、2010 年に週刊誌に野球賭博に関与したと報じられ、警察の取り調べを受け相撲協会から解雇されました。その後 元横綱大鵬との養子縁組も解消し、三女とも離婚しました。( されました ? ) ところで、故 二子山親方 ( 元大関 貴ノ花 ) の息子二人がそれぞれ 65 代横綱 貴乃花と、66 代横綱 ・ 若乃花になりましたが、これは例外中の例外であり、祖父で第 45 代横綱 初代 若乃花から よほど素晴らしい相撲取りの遺伝子を、隔世遺伝により受け継いでいたに違いありません。 江戸時代の大きな商家も、 女系優先 でした 。たとえ実子でも生まれた男の子は無条件で 「 廃嫡 」 ( はいちゃく、家督相続権をなくすこと ) させ、母親自身が 「 腹を痛めて生んだ女子 」 に財産を相続させ、自分の店で最も有能な店員を婿 ( むこ ) に選ぶ 「 女系優先経営主義 」 を取りました。この女系中心主義は大坂 ( 阪 ) 以外にもかなり残っていて、東京でも昭和初期までは町の金融機関は 「 婿取り 」 ではない商家には、金を貸さない場合が多かったといわれています。 現在は法人企業の格付けには ムーディーズ ・ スタンダード & プアーズ ・ 格付投資情報センター、フィッチ ・ レーティングスなどがありますが、1940 年頃までの東京における企業の 「 格付け 」 方法には、当主や社長が 「 婿取り 」 か否か ということが かなり重要な要素でした。 当主が婿 ( むこ ) であるという利点は、 実子 ( 息子 ) 相続企業に対する 危惧感 ( きぐかん、うまくいかないのではないかと危ぶむ ) の大きさに比べて 、それだけで社会的 ・ 業界内の 信用度が大でした 。 ( 10−2、危惧が現実のものに )  大王製紙の創業家の孫である会長の井川意高 ( いかわ もとたか、48才 ) が 、グループの子会社 7 社から 約 55 億 3 千万円 を無担保で借り入れ海外の 賭博に注ぎ込み 損害を与えたとして、特別背任罪に問われた上告審で 最高裁 第 3 小法廷は、 2013 年 6 月 26 日に上告を却下し前会長の 懲役 4 年の実刑 が確定しました。
会社の公金と自分の家の金とを区別できない創業家の三代目当主と、犯行に対して同族企業である子会社 7 社の取締役 ・ 監査役などは、組織としての チェック機能が全く作用しませんでしたが、これは同族企業の陥りやすい宿命とも言うべきものでした。ちなみに両親の井川高雄 ・ 弥栄子夫妻には男の子が 二人いて、被告の意高 と次男の高博 ( 大王製紙取締役 ) でしたが、女系優先経営主義とはこのような危険を予め避けるために考えだされた 「 先人たちの知恵 」 でした。
パナソニック ( 旧 ・ 松下電器産業 ) の創業者である松下幸之助は和歌山の小学校を 4 年で中退し、9 才で丁稚 ( でっち ) 奉公に出されましたが、そこから身を興して、生涯に 5 千億円の資産を築いたと推定されていますが、彼が後継者に選んだのは、娘 幸子の婿となった 三井銀行員の松下正治 ( まさはる ) でした。
大王製紙の創業家の孫である会長の井川意高 ( いかわ もとたか、48才 ) が 、グループの子会社 7 社から 約 55 億 3 千万円 を無担保で借り入れ海外の 賭博に注ぎ込み 損害を与えたとして、特別背任罪に問われた上告審で 最高裁 第 3 小法廷は、 2013 年 6 月 26 日に上告を却下し前会長の 懲役 4 年の実刑 が確定しました。
会社の公金と自分の家の金とを区別できない創業家の三代目当主と、犯行に対して同族企業である子会社 7 社の取締役 ・ 監査役などは、組織としての チェック機能が全く作用しませんでしたが、これは同族企業の陥りやすい宿命とも言うべきものでした。ちなみに両親の井川高雄 ・ 弥栄子夫妻には男の子が 二人いて、被告の意高 と次男の高博 ( 大王製紙取締役 ) でしたが、女系優先経営主義とはこのような危険を予め避けるために考えだされた 「 先人たちの知恵 」 でした。
パナソニック ( 旧 ・ 松下電器産業 ) の創業者である松下幸之助は和歌山の小学校を 4 年で中退し、9 才で丁稚 ( でっち ) 奉公に出されましたが、そこから身を興して、生涯に 5 千億円の資産を築いたと推定されていますが、彼が後継者に選んだのは、娘 幸子の婿となった 三井銀行員の松下正治 ( まさはる ) でした。
 ところで平成 25 年 6 月 30 日をもって銀座の デパートの老舗 ( しにせ ) 松坂屋が閉店しましたが、大正 13 年 ( 1924 年 ) の 銀座店開店から 88 年でその輝かしい歴史に幕を下ろしましたが、写真は開店当時のものです。
それまでの デパートの常識を破り松坂屋銀座店では全館 土足 入館を可能とした 初めての百貨店となりましたが、 それまでは 履き物を脱いで デパートに入館したのだそうです 。
ところで平成 25 年 6 月 30 日をもって銀座の デパートの老舗 ( しにせ ) 松坂屋が閉店しましたが、大正 13 年 ( 1924 年 ) の 銀座店開店から 88 年でその輝かしい歴史に幕を下ろしましたが、写真は開店当時のものです。
それまでの デパートの常識を破り松坂屋銀座店では全館 土足 入館を可能とした 初めての百貨店となりましたが、 それまでは 履き物を脱いで デパートに入館したのだそうです 。
[ 11 : 履き物を脱ぐといえば、今は昔 ]飛行機による旅が未だ一般的ではなく、若い人は生まれて初めて新婚旅行の際に飛行機に乗り、お年寄りは 「 冥土の土産話 」 に乗る程度であった昭和 40 年 ( 1965 年 ) 代初めのこと、搭乗する際に 履き物を脱いで乗ろうとしたお年寄りや新婚さんがいたことを思い出しました 。 機内に敷いてある 「 じゅうたん 」 の上を、土足で歩くのは いけないとでも思ったのでしょうか ?。 半世紀近く昔のことでした。
|
 お江戸日本橋、七つ立ち / 初のぼり 行列 揃えて あれわいさのさ / こちゃ高輪 夜明けて提灯消す / こちゃえこちゃえ
お江戸日本橋、七つ立ち / 初のぼり 行列 揃えて あれわいさのさ / こちゃ高輪 夜明けて提灯消す / こちゃえこちゃえ