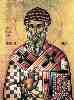聖徳太子異聞 ( 続き )
景教 ( けいきょう ) とは、 キリスト教の 一宗派である ネストリウス ( Nestorius ) 派に対する中国での呼び名ですが、5 世紀のこと ビザンチン帝国 ( Byzantine 、東 ローマ帝国 ) の首都 コンスタンチノープル ( Constantinople 、現 ・ イスタンブール ) に、シリア出身の 大主教 ( Arch-Bishop 、アーチ ・ ビショップ ) の ネストリウス ( Nestorius 、380 頃 ?~451 年 ) がいました。 彼は聖母 ( マリア ) と、 イエス ・ キリストの 神性 ( しんせい、神としての性質 ・ 属性 ) を否定したために、431 年の第 3 回宗教会議で異端 ( いたん、正統とされる キリスト教の教義から外れている ) とされ破門されました。
そこで彼は 聖母 マリアや イエスが 人間であること を教理の基本とした、新しい キリスト教の 一宗派である ネストリウス派を創設しました。それによれば、 イエス ・ キリスト の 神格 ( 神としての資格 ) は、新約聖書の前半に記されている イエスの言行 ・ 行動の記録である 、 マタイによる福音書、マルコによる福音書、ルカによる福音書、ヨハネによる福音書の 四つの福音書 に宿り 、イエスの 人格は ゴルゴダの丘で十字架に架けられ 滅んだ 肉体 に宿っていた と規定しました。 そこから導き出された考え方からすれば、カトリック教徒が崇拝する キリストを生んだ 「 マリア 」 は神の子を産んだ 聖母 ではなく、単なる普通の人間でした。
この景教が中国で流行したことを示す記念碑が、西安の陜西省立博物館に展示されていますが、石碑にある 大秦景教流行中国碑 の意味について、秦 ( しん ) とは始皇帝が紀元前 221 年に興した国名のことではなく、 大秦 ( たいしん ) とは漢代の中国人が、 ローマ帝国あるいはその東方領土を呼んだ名称です。 同様に中国とは毛沢東による共産革命の結果成立した中華人民共和国 ( 1949 年 ) の意味ではなく、当時の国とは城壁で囲まれた地域 ( 主に都市 ) のことであり、 中国 とは中央にある都 ( みやこ )つまり西安か長安のことで、そこで景教が流行したことの記念碑でした。
参考までに ネストリウス派の キリスト教が中国にもたらされたのは、唐の時代 ( 618~907 年 ) の貞観 9 年 ( 635 年 )のことで、アッシリア東方教会の使いで ネストリウス派主教の アラポン( 阿羅本 ) が宣教団を率いて首都の長安へ向かい、キリスト教を中国に布教したのが最初でした。 唐や 元 ( げん ) の王朝の庇護を受けて 一時期信仰が盛んになりましたが、右の写真では本来あるべき蓮の花の台座ではなく、十字架の上に仏像か何か分からぬ像が鎮座しています。
[ 8 : 摂政皇太子の業績 ]
聖徳太子 ( 574~622 年 ) が伯母に当たる推古天皇 ( 554~628 年 ) の摂政皇太子として女帝を補佐したのは、推古元年 ( 593年 ) 4月からでしたが、彼はこの年の秋 10 月には早くも大阪 ・ 難波津 ( なにはの つ ) に四天王寺 ( してんのうじ ) を建立しました。
これまで中国への従属国でした日本の王は、貢ぎ物を持つ使者を派遣する朝貢 ( ちょうこう、ごきげん伺い ) をして、その地位を中国の皇帝に認めてもらう冊封体制 ( さくほうたいせい、注: 参照 ) にありましたが、 607 年には小野妹子 ( おののいもこ、男性 ) を第 1 回遣隋使 ( けんずいし ) として中国に派遣して有名な国書を随に送り、 冊封体制から離脱しました。
注 : ) 冊封体制の証拠、金印 ( 8-1、日出ずるところの天子、つつが無きや )
小野妹子が随 ( ずい ) に手渡した国書については 日本書紀に記録が無く 、聖徳太子の死後に完成した相手側の隋書 ( 本紀 5 巻、列伝 50 巻、636 年成立 )にありますが、その後 遣唐使により随書の 写本が日本に持ち帰られました。隋書の列伝 ( れつでん、人々の伝記を連ね記したもの ) 46 ・ 東夷伝 ・ 倭国の項によれば、
其國書曰日出處 天子 致書日沒處 天子 無恙 中華思想によれば、天子と自称できるのは 中国の皇帝だけ でしたが、アジアの辺境にある小国の日本の天皇が天子を自称し、大国の随 ( ずい ) に対等な国書を送り、 日本の国威を発揚した と太平洋戦争中に小学校で習いました。 これに対して随の支配者である煬帝 ( ようだい ) は、
蛮夷書有無礼者、勿復以聞つまり、使者を斬れと命じました。しかし外交関係者から朝鮮にある高句麗 ( こうくり ) への第 1 回遠征 ( 612 年 ) を前に、日本を敵に回すのは得策ではなく、今は時期が悪いと諭 ( さと ) され思い留まりました。
当時から世界はもとより 新潟、秋田、山形県などの河川流域には、野 ネズミなどに寄生して ツツガムシ病 ( 恙虫病 ) を媒介する ダニ 目 ( もく ) ・ ツツガムシ 科 ( か ) の節足動物 ( ダニ の 一種 ) である ツツガムシ ( 恙虫 ) が生息していました。
春から秋にかけてその地域や山野を歩くと衣服に付着した ダニ ( 成虫の体長 0.2 ~ 1 ミリメートル ) に喰われて 「 ツツガ虫病 」 に感染しましたが、昔は死亡率の高い病気として恐れられていました。 恙 ( つつが ) とは、本来病気や災難を意味する言葉ですが、一説によれば ツツガムシ に由来する説もありました。 太平洋戦争の敗戦後に テトラサイクリン などの抗菌薬 ( 抗生物質では効果がない ) が開発され、また自然環境の変化により感染者や死亡者が減りましたが、厚生労働省によると、平成 23 年 6 月 26 日現在、全国 ( 現在は沖縄 ・ 北海道を除く全国に広がっている ) の感染者数は 143 人で 、昨年同期より 46 人多く、死者は青森と新潟で 少なくとも 3 人に上ります 。 ( 8-2、お経の解説書にある言葉 ) ところで 日出処、日没処 ( 日出ずるところ、--- ) の表現については、実は タネ本 がありましたが、それは ナーガール ・ ジュナ、漢訳名では 龍樹 ( りゅうじゅ、 ) という インドの大乗仏教の僧 ( 150~250 年頃 ) が著述した 大智度論 ( だいちどろん ) の中でした。 如経中説、 日出処 是東方、 日没処 是西方、日行処是南方、日不行処是北方 ( 以下 省略 )大智度論とは大乗仏教 ( だいじょうぶっきょう、注 参照 ) の教典である 摩訶般若波羅蜜経 ( まか はんにゃ はらみつ きょう、大品般若経 ともいう ) についての 百 巻におよぶ注釈書ですが、そこでは大乗仏教に重要な 空 ( くう ) の思想 を形成しました。
注 : )そのため龍樹 ( りゅうじゅ ) は日本の仏教のほとんどの宗派において重要な存在とみなされ、 八宗 ( 仏教の 八つの宗派 ) の祖 と呼ばれ、中には 龍樹菩薩 ( りゅうじゅ ぼさつ ) と崇 ( あが ) める宗派もあります。 聖徳太子には仏教を学ぶために 595 年に朝鮮半島から招いた高句麗 ( こうくり ) の僧、 慧慈 ( えじ ) や百済 ( くだら ) の僧、 慧聡 ( えそう ) が ブレーン ( Brain、頭脳 ・ 相談役 ) にいたので、彼らの大智度論 ( だいちどろん ) に関する知識から、この表現を随に宛てた国書に取り入れ、国書としての体裁を整えたとされます。 日本書紀には東 ・ 西の文言をそのまま使った国書もあります。推古 16 年 ( 608 年 ) 9 月辛巳 ( かのと み、11日 ) の条に
東 天皇敬白 西 皇帝 ( 以下省略 )これは最初の国書 「 日出処天子 」 に比べて低姿勢な書き出しですが、相手の不興をかったので日本側も態度を変えたのかもしれません。
聖徳太子は遣隋使を通じて中国文化を取り入れるために多くの留学生を隋に送りましたが、先進文化を取り入れ飛鳥文化の開花をもたらすなど内政 ・ 外交面で十分な成果を上げました。しかし推古女帝はなぜか 彼を 28 年間 も 摂政の地位 に留めたままで、 譲位 しませんでした。 結局 聖徳太子は女帝より先に 49 才 で亡くなりましたが、摂政の地位に長年在りながら遂に天皇になれずに死んだ 不運な人であり 、悲劇の人 ( 次項 ) でした 。 日出ずる国の左翼市民運動家 ・ 親中 ・ 親北朝鮮派の 空き菅 総理 と同じで、 女帝は一旦手に入れた権力 ・ 地位を絶対に手放さず、聖徳太子の死後も自分が死ぬまで 更に 7 年間 も天皇の地位にとどまり続けました。彼女はそれまでにも皇后の地位に 16 年間、その後 天皇の地位に 36 年間 ( 在位 592~628 年 ) も留まり続け、当時としては長寿の 75 才で亡くなりました。
日清戦争 ( 1894~95 年 ) の際に突撃 ラッパを吹きながら被弾し戦死した ラッパ手の 木口小平 ( きぐち こへい ) のことを、現在 74 才以上の人は小学校の教科書で習ったはずですが、教科書によれば、
キグチコヘイハ テキノ タマニ アタリマシタガ、 シンデモ ラッパヲ クチカラ ハナシマセンデシタつまり死んだ後も ラッパ手としての職責を果たし、人々の模範とされました。 ところで 死んでも離さなかった点で 彼に少しも引けを取らなかったのが皇位に執着した推古女帝で、死期が近づいても後継天皇の指名をしませんでしたが、あの世でも天皇のままで いたかった からに違いありません、 その権力欲には脱帽 ! 。 ここで得た教訓とは、
美人 ( 姿色端麗 ) であることと、その人が持つ 権力に対する異常な 執着心 の強さ とは、全く関係が無いこと。 ( 8-5、聖徳太子の悲哀 ) 聖徳太子は前述したように、摂政でありながら伯母から 28 年間も譲位されずに 冷や飯を喰わされ続けていた ので将来を悲観し、人生の後半にはこれまでの人生に虚しさを感じて、政治よりも仏教に精進 ( しょうじん ) し、下記の言葉を残しました。
世間 虚仮 ( せけん こけ ) 、唯仏是 真 ( ゆいぶつ ぜ しん ) 
聖徳太子の没後、妃 ( きさき ) の 1 人でした橘 大郎女 ( たちばなの おおいらつめ ) が、太子と太子の母后 ( 母であった皇后、= 穴穂部間人皇后 ) の天寿国 ( てんじゅこく、極楽浄土 ) にある姿を画工に描かせ、それに刺繍 ( ししゅう、縫い取り ) させて作らせた 天寿国曼荼羅 ( てんじゅこく まんだら ) の繍帳 ( しゅちょう ) に描かれていた銘文にあるもので、太子が述べたとされる言葉です。
[ 9 : 聖徳太子の死 、自殺 ? ]
法隆寺の金堂には国宝の 釈迦三尊像 ( しゃか さんぞん ぞう ) がありますが、その 光背 ( こうはい ) には 仏像造作の経緯 が刻まれています。
光背 ( こうはい ) とは、仏像などの背後についている、仏身から放射される光明 ・ 後光 ・ オーラを象徴的に表した装飾のことですが、その背面に刻まれた銘文を光背銘 ( こうはいめい ) といいます。その原文の一部を示すと、そこには聖徳太子が死亡した経緯が簡単に記されています。
法興元卅一年歳次辛巳十二月鬼前 太后崩 明年正月廿二日 上宮法皇 枕病弗腦 干食王后 仍以勞疾並著於床時王后王子等及與諸臣深懐愁毒共相發願仰依三寶當造釋像尺寸王身蒙此願力轉病延壽安住世間 ( 以下省略 )[ その概略の意味 ] 法興元 31 年 12 月に鬼前 太后 [ きぜんのおおきさき、= 聖徳太子の母親 ] が亡くなり、翌年 1 月 22 日に上宮法皇 ( うえのみやほうこう、= 聖徳太子 ) が病気になり、看病していた干食王后 [ かしわでの おうごう = 膳 大郎女 ( かしわでの おおいらつめ ) ] もまた心労と疲労から並んで床についた。 そこで王后 ・ 王子をはじめ、所縁 ( ゆかり ) の諸臣らが与 ( とも ) に深く愁 ( うれ ) い毒 (なや) み、共に相い發願 ( はつがん ) すらく、「 仰ぎて三寶 ( さんぼう、仏 ・ 法 ・ 僧 ) に依 ( よ ) り、當 ( まさ ) に釋像の尺寸王身( 太子の背丈と同じ大きさの釈尊像 ) を造る。此の願力を蒙 ( こうむ ) り、病を轉 ( てんじ、快方に向かい ) じ壽を延べ ( よわいを のべ、年齢を重ね ) 、世の間に安住したまうことを ( 以下省略 ) と祈願しました。 ちなみに廏戸皇子 ( 聖徳太子 ) の死後 約 100 年後に成立した日本書紀の巻 22、推古紀によれば、
廿九年春二月己丑朔癸已半夜廏戸豊聡耳皇子命 薨 干斑鳩宮。是時諸王諸臣及天下百姓悉長老如失愛児而鹽酢之味在口不嘗少幼如亡慈父母以哭之声満於行路 ( 以下省略 )[ その意味 ] 推古 29 年 ( 622 年 ) の春 2 月の己丑 ( つちのとの うし ) の朔 ( さく ) 癸巳 ( みずのとの み、5 日 ) の夜半に、廏戸豊聡耳皇子命 ( うまやどの とよとみみの みこの みこと ) が斑鳩宮 ( いかるがのみや ) で 薨 ( こう、3 位以上の貴人の死に対していう ) じた。 このとき、諸王、諸臣および国内の百姓 ( おおみたから ) はみな、老人は愛児を失ったように塩や酢を口にしてもその味がわからず、幼少の者はやさしい父母をなくしたように泣き悲しみ、その声がちまたにあふれた。( 以下省略 ) とありましたが、肝心の聖徳太子および前日に死んだ妃 ( きさき ) の 1 人である膳 大郎女 ( かしわでの おおいらつめ )の 病気については何も記されていませんでした 。 ところが平安時代 ( 794~1192 年 ) の初期、つまり聖徳太子の死後約 200 年後に書かれた 上宮聖德太子傳 補闕記 ( じょうぐう しょうとくたいしでん ほけつき ) によれば、
壬午年二月廿二日庚申 太子 無病 而薨 時年 四九つまり 事故死 と書かれていました。さらに約 300 年後の 917 年に記された 聖徳太子伝暦 ( でんれき ) によれば、
廏戸皇子は斑鳩宮 ( いかるがのみや ) で妃に入浴させ、自分も入浴した後に新しい衣服に着替え、妃に今夜死ぬつもりだが 一緒に死ぬか ? と尋ねたという 。二人は床に入り翌朝起きてこないので家臣が寝殿の戸を開けたところ、二人とも死んでいた。即ち 自殺 とありました。 ここで前述した ( 6-3 ) 、 「 歴史資料評価の原則 」 を思い出してください。時の経過と共に、後の世に書かれた資料の信頼性が低下することを。
ちなみに聖徳太子の遺体は 2 ヶ 月の間に相次いで亡くなった母親の穴穂部間人大妃 ( あなほべの はしひとの おおきさき ) と 、妃( きさき ) である膳大郎女 ( かしわでの おおいらつめ ) と共に、 、大阪府 ・ 南河内郡 ・ 太子町 ・ 太子 ) に 直径 50 メートル、高さ 10 メートルの円墳である 磯長陵 ( しながの みささぎ ) を造り、三人の遺体を切石を用いた横穴式石室に葬る 三骨一廟 ( さんこつ いちびょう ) の陵墓 ( りょうぼ、) に合葬しました。
聖徳太子の死後、蘇我氏の専横 ( せんおう ) はますますつのり、蘇我蝦夷 ( そがの えみし ) は子の入鹿 ( いるか ) に大臣 ( おおおみ ) の位である紫冠を授けました。推古天皇が後継者の指名をせずに 628 年にようやく死ぬと、ただちに皇位継承者問題が起きましたが、その有力候補には 聖徳太子の息子である山背大兄王 ( やましろの おおえの おう、?~643 年 ) と、第 30 代、敏達 ( びたつ ) 天皇の息子である田村皇子( たむらのみこ ) の二人がいました。 蘇我蝦夷 ( そがの えみし ) にとって リモコンが容易な田村皇子を次の天皇に推挙したので、第 34 代 舒明天皇 ( じょめい てんのう、在位 629~641 年 ) に即位しました。
蘇我氏にとっては有力な皇位継承者候補であった山背大兄王とその一族の存在が、今後の政治支配にとって邪魔であり取り除く必要があったので、643 年 11 月に蘇我入鹿の軍が斑鳩宮 ( いかるがのみや、現在の法隆寺 ) を襲い、山背大兄王( やましろの おおえの おう ) が自殺し 一族 15 人も自殺や殺された結果、聖徳太子の血統は全て途絶えましたが、聖徳太子の 死後 21 年目のことでした 。 彼が遺 ( のこ ) した言葉である 世間虚仮 ( せけん こけ ) 、 唯仏是真 ( ゆいぶつ ぜしん )が思い出されます。
この間 蘇我入鹿の専横はますますひどくなり、蝦夷 ( えみし ) の家を上宮門 ( うえのみかど ) 、自分の家を谷宮門 ( はざまのみかど ) と称し、子供たちを王子 ( みこ ) と呼ばせるなどの僭越 ( せんえつ、身分を越えた ) な態度を示しました。 山背大兄王の一族滅亡事件から 2 年後の 645 年 6 月 12 日 、この日は 十干 ( じつかん ) ・ 十二支 ( じゅうにし ) による記日法で、乙巳 ( きのと み )、音読みで ( いっし ) の日に当たりましたが、飛鳥板蓋宮 ( あすか いたぶきのみや )の大極殿 ( だいごくでん、天皇が政務を執る所 ) において、来日した 三韓 ( 新羅、百済、高句麗 ) の使者に対する儀式が行われました。
その機会をとらえて中大兄皇子 ( なかの おおえの みこ ) 、中臣鎌足 ( なかとみの かまたり )などが宮廷 クーデターを起こして、専横を極めた蘇我入鹿 ( そがの いるか ) を殺害しましたが、それを聞いた蘇我蝦夷 ( そがの えみし ) も甘檮岡 ( あまかしのおか ) に建てた広壮な邸宅で自殺しました。 上図は江戸時代前期を代表する大和絵画家である、住吉如慶 ・ 具慶 ( すみよし じょけい ・ ぐけい ) 親子の合作によって描かれた 乙巳 ( いっし ) の変 の絵で、斬られた蘇我入鹿の首が飛び、左上で逃げまどう女性は第 35 代、皇極 ( こうぎょく ) 女帝です 。
これにより蘇我稲目 ( そがの いなめ ) に始まり、馬子 ( うまこ )、蝦夷 ( えみし )、入鹿 ( いるか ) の四代にわたり、古代から飛鳥時代初期に掛けての政治に権力を振るってきた蘇我一族は滅亡しました。中大兄皇子 ( 後の第 38 代、天智天皇、在位 668~671 年 ) は日本初の年号を大化と定めて、 大化改新 ( たいかの かいしん ) をおこない政治を初め諸制度を改新し、聖徳太子が目指した外国の文物を取り入れ日本を改革する基礎を作りました。
[ 10 : 聖徳太子の母親の伝説 ]日本の歴史で間人皇女 ( はしひと/はしうどの ひめみこ ) といえば、聖徳太子の生母となった穴穂部間人皇女( あなほべの はしひとの ひめみこ )と、前述した 「 大化の改新 」 をおこなった中大兄皇子 ( なかの おおえの みこ、後の天智天皇 ) の妹で、第 36 代、孝徳天皇に嫁いだ間人皇女がいますが、もちろん両者は別人です。ここでの話は聖徳太子の生母に当たる、穴穂部間人 ( あなほべの はしひと ) 皇后に関することです。( 10-1、冬の味覚、カニ )
関西に住む人々にとって冬の日本海の味覚といえば松葉 ガニ ( 別名 ズワイガニ、地域によっては越前 ガニなどともいう ) ですが、私も若い頃は毎年冬になると凍結した道路の走行に備えて、未だ禁止されていなかった スパイク ・ タイヤを車の駆動輪に履き、さらに積雪に備えて タイヤ ・ チェーンを車に積んで雪の多い日本海側の温泉旅館や民宿などに カニを食べに行きましたが、当時は舞鶴 ・ 若狭自動車道などありませんでした。 ある年の冬のこと、 妻と娘と一緒に家から 4 時間程度で行ける京都府 ・ 網野町( 現 ・ 京都府 ・ 京丹後市 ・ 網野町 ) にある 「 夕日ヶ浦温泉 」 に車で行きましたが、途中で雪が降り出したので近道の地方道から、交通量の多い国道 9 号、426 号線経由に コースを変更しました。兵庫県 ・ 豊岡市内では積雪が 20 センチとなり、タイヤ ・ チェーンを履き のろのろ運転した結果、予定より 2 時間遅れてようやく目的地の旅館にたどり着きました。 ( 10-2、「 間人 」 の いわれ について )
ところで 「 夕日ヶ浦温泉 」 から北東へ 18 キロ 離れた丹後半島の北西側に 間人 という地名がありますが、これを 「 たいざ 」 と正確に読める人は近郊の人か、小さな間人漁港から水揚げされ美味で知られる ブランド の、 間人 ガニ ( たいざ ガニ ) に興味がある人に限られます。
間人 ( たいざ ) 漁港で水揚げされる 「 間人 ガニ 」 には品質を保証する プラスティック 製の 「 緑色の タグ 」 が、切断しなければ外れない インシュロック ( Insulok 、結束バンド )で取付けられていますが、その片面には カニの マークと京都の文字、 もう一方の面には 「 たいざ ガニ 」 の文字と 捕獲した漁船名が記されています。
一説によれば 間人( たいざ ) という地名は、聖徳太子の生母である穴穂部間人 ( あなほべの はしひと ) 皇后にちなむとされ、その地には間人皇后の石像や石碑が建てられています。間人 ( はしひと ) 皇后ゆかりの碑文には、
第 31 代 用明天皇の御后 ( おきさき ) であり、聖徳太子の母君であらせられた穴穂部間人皇后は 6 世紀のおわり頃、大和における蘇我 ( そが ) ・ 物部( もののべ ) 氏の争乱をここ皇后の御領であった大浜の里に避けられた。( 以下省略 )豪族同士の争乱が止んだので、間人皇后は大和の斑鳩宮 ( いかるがの みや ) に戻ることになりましたが、その際にこの地に名残りを惜しみ、自分の名前である 間人 ( はしひと ) を 地名にするように言われました。しかし人々は畏 ( おそ ) れ多いとして 皇后が ( その地を ) 退座した ことから、間人の読みを 「 たいざ 」 としたのだそうです。 しかし、「 日本書紀 」などの歴史資料には、穴穂部間人 ( あなほべの はしひと ) 皇后が争乱を避けて、丹後国に避難したとの記述は存在しませんでした。
|